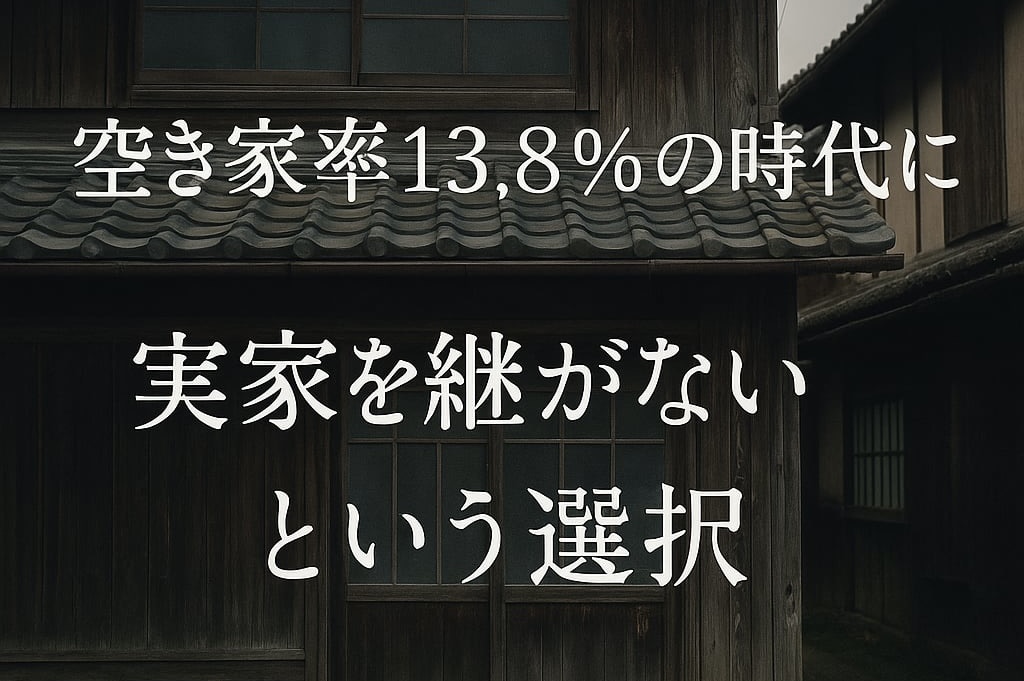
空き家率13.8%の時代に「実家を継がない」という選択 —— 地方の実家じまい、どこから始める?
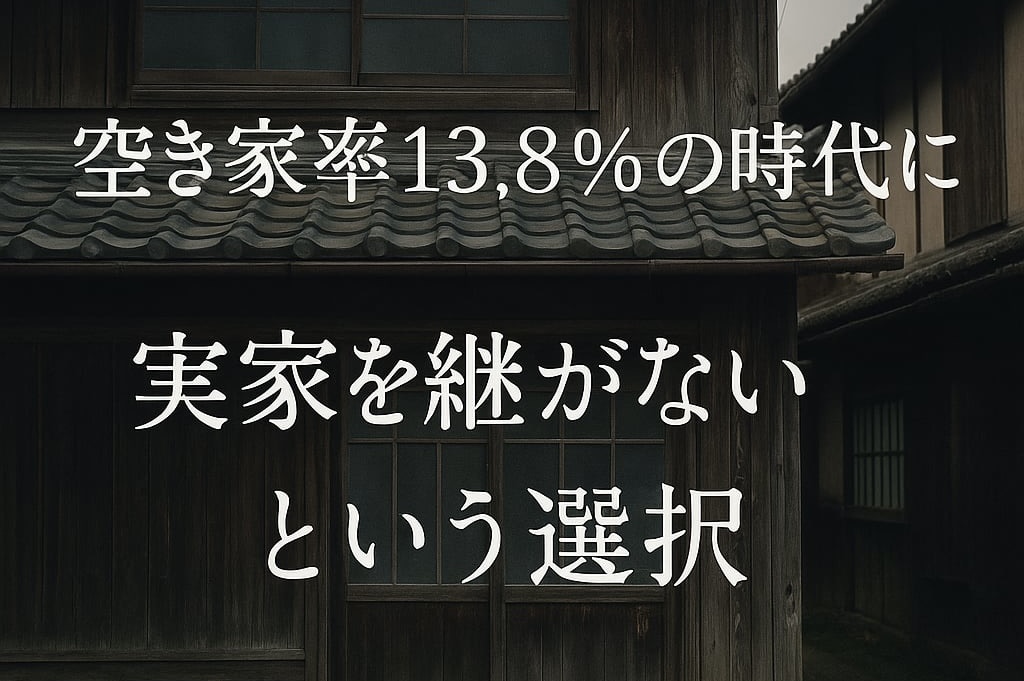
目次
実家じまいを考えることになった日
先日、母とともに高知県の某市を訪れました。
母の実家、つまり私の祖母と叔母が暮らす家の今後について話し合うためです。
いわゆる「実家じまい」。
けれど、訪問の前日に祖母が自宅で転倒し、大腿骨を骨折。
私たちは祖母の手術を待つ病院の待合室で、家のことや、これからの家族の暮らし方について話すことになりました。
それは突然やってきた、「この家、どうする?」という問い。
今までどこか遠くにあった“親の家問題”が、目の前に降ってきた瞬間でした。
進む高齢化と空き家の増加
実家じまいという言葉を聞いたことがある方も多いと思います。
親が高齢になったり、介護や住み替えを考えるタイミングで出てくるのがこのテーマです。
では、なぜ今「実家をどうするか」がこれほど大きな問題になっているのでしょうか?
総務省「住宅・土地統計調査(2018年)」によれば、日本全国の空き家率は13.6%。
約7戸に1戸が空き家という計算になります。
しかも、少子高齢化が進む地方ではこの割合がさらに高く、人口減少とともに空き家の増加が顕著です。
2023年時点では全国の空き家総数は900万戸を超えるとも言われています。
2030年には空き家率が20%を超えるという予測もあり、これはもはや「一部の人の問題」ではありません。
誰も住まなくなった家に、未来はあるのか
私たちが訪れた高知県某市は、観光地としての魅力もありながら、過疎化や高齢化が進む地域でもあります。
母の実家も例外ではなく、長年祖母と叔母の二人暮らしが続いてきました。
しかし、祖母が入院し、叔母だけが1人残される状況になった今、
「この家に、誰が住むのか?」「管理できるのか?」という現実が、目の前に突きつけられました。
地方の古い家には、家族の思い出や暮らしの記憶が詰まっています。
けれど、不動産としての価値は低く、「売ろうにも売れない」「貸したくても借り手がいない」といった声も多く聞かれます。
母は「大阪に連れて帰った方が安心」と言うものの、
長年住み慣れた土地を離れることは、祖母や叔母にとって簡単な決断ではありません。
実家じまい、何から始めればいいのか
実家じまいは、「売るか残すか」だけの話ではありません。
実際には、もっと複雑で、もっと感情的な問題が絡んできます。だからこそ、何から手をつけてよいかわからず、先延ばしにされがちです。ここでは、最初のステップとして考えたいポイントを整理します。
登記内容の確認
まず最初にすべきは、その家の名義人は誰かを把握することです。
古い家では登記が祖父母のままになっていることも少なくありません。
この状態では売却も貸し出しもできませんので、相続登記(名義変更)が必要です。
相続人間の話し合い
名義を誰にするか、家をどうしたいか——。
兄弟姉妹がいる場合、早めの話し合いが鍵になります。
揉めないよう、親が元気なうちに「誰がどこまで関わるか」を決めておけるとベストです。
空き家バンクなどの利用検討
地方自治体が運営する「空き家バンク」は、民間不動産会社では扱いにくい物件にも対応してくれる可能性があります。
特に築年数が古い物件や山間部の家は、地域おこし協力隊・移住希望者などニーズがある場合も。
自治体の担当窓口に相談してみるのがおすすめです。
解体という選択肢とその費用感
「売ることも貸すこともできない場合、いっそ壊して更地にする」という判断をするご家庭もあります。
しかし、木造住宅の解体にはそれなりの費用がかかります。
一般的な目安は以下の通りです:
- 木造住宅(30坪前後)で、約100〜150万円
※立地やアスベストの有無、重機の入りやすさにより増減します - 解体後も、固定資産税の軽減措置がなくなることに注意(住宅が建っていると1/6になる制度)
また、地方自治体によっては「空き家解体補助金」が出るケースもあるため、事前に役所に相談するのがオススメです。
私の祖母と叔母が暮らす自治体では、坪単価:約33,000円前後が相場のようです。
最大120万円・費用の8割までの補助が可能。つまり、もし実質負担が約100万円 なら→ 補助利用で20万円前後になるかも。
感情の整理も“第一歩”
忘れてはならないのが、感情的なハードル。
親にとっては長年暮らした家を手放すという現実。
子にとっては思い出の詰まった家を「無人の物件」として扱うことへの葛藤。
だからこそ、感情を否定せずに、家族の“未来の暮らし”を軸に判断することが大切です。
未来の空き家をつくらないために
私たち家族の決断は、まだこれからです。
祖母の容体や、叔母のこれからの暮らし方。
そして、母の気持ちと大阪との距離感。簡単に答えが出る話ではありません。
でも、この経験を通じて私が感じたのは——
「家のことは、元気なうちに考えたほうがいい」というシンプルな事実です。
家の問題は、相続や登記といった制度だけでなく、人の生活そのものとつながっています。
誰も住まなくなった家が、地域の負担になってしまう前に。
親の希望や、自分たちの暮らしを尊重しながら、少しずつ準備を始めていく。
それが、私たち世代にできる「小さな空き家対策」なのかもしれません。
あなたのご実家は、どんな状況ですか?
いつかやってくる「実家の決断」。
「そのとき」ではなく、「今」だからこそ話せることがあるかもしれません。